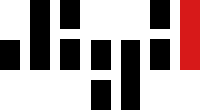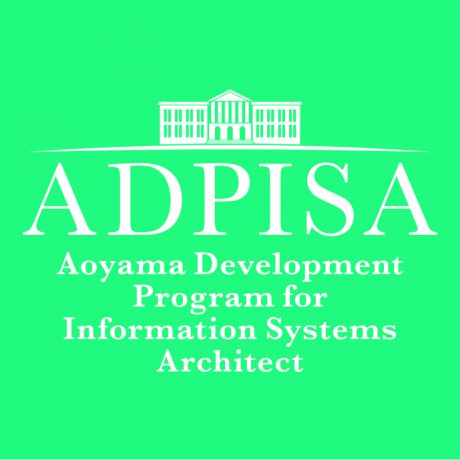アメリカから来た旧友
翌日2月23日(日曜日)の14時、大学の同窓会が東京・丸の内にあるホテルの小宴会場を借りて行われた。参加者は同じ時期に学んだゼミ生や関係者を中心に、50名ほど。佐々木が仲間と会うのは、30年ぶりのことだ。大学時代の恩師も健在だった。
「よう、久しぶりだな」「おお、お前も元気にやっていたか」
話してみると、見た目ほどはお互い中身は変わっていない。気の置けないあの頃の仲間の顔が次々と思い浮かんできた。その中の1人に、旧友の遠藤匠(たくみ)がいた。スキーやテニスといったスポーツを一緒に楽しんだ親友である。
ただ、大学を卒業後、しばし疎遠になった。遠藤がすぐに就職せず、日本を離れ、2年ほどバックパッカーとして世界各地を放浪していたからである。その後、日本で、外資系の商社に入社したという。それから単身アメリカに渡り、M&Aを学んで現地でビジネスを立ち上げた。現在は、アメリカ東海岸で、経営コンサルタントとして事務所を構えているという。
「修か。変わってないな」「匠は、貫禄ついたな」
談笑しながら佐々木はふと、匠なら、例のITプロジェクトについて、何か適切なアドバイスをしてくれるかもしれないな、と思った。この日の同窓会は、17時で散会になり、そのあと二次会に移行した。佐々木も懐かしい面々と旧交を温めた。二次会も19時でお開きとなり、別れを惜しみつつ、帰宅する人、三次会に行く人、三々五々に散らばった。
帰り際、佐々木は改めて、遠藤に声をかけた。
「実は、匠に聞きたいことがあってさ」
「どんなことだ」
「仕事のことなんだ。同窓会の場で無粋なんだが。予定があれば改めるけど」
「水くさいこと言うなよ。良ければ、もう一軒行こう」
佐々木は遠藤とともにタクシーに乗り、新橋駅に近い銀座八丁目のこざっぱりとした居酒屋に河岸を変えた。
ぬる燗の純米酒を互いに注ぎながら、佐々木は、改めて、現在立て直しを迫られ思い悩むITプロジェクトの経緯を遠藤に語った。遠藤は、佐々木の話を頷きながら盃を傾けた。
佐々木が一通り説明を終えたあと、遠藤はこう尋ねた。
「修の会社では、ビジネスとシステムを橋渡しするITエンジニアを備えていないようだな。いないのなら、それはなぜなんだ?」
「うちだけでなくて、日本の企業は多かれ少なかれ同じ状況だと思う。大企業でさえIT部門はベンダーとの調整役がメインで、技術のあるエンジニアと呼べる人材は少ないんだ。俺もそういう役回りがほとんどで、業務部門のシステムにはほとんど手が出せない。販売部などの連中からは、情報システム課はコストセンター、と思われているんだよ」
「取引先のベンダーと揉めているのか。そもそも、その前に結んだ契約にはなんて書かれているんだ?」
「ベンダーとの契約は、うちの法務部が担当しているが、プロジェクトの詳細な事項には触れられていない。数枚で終わっている簡単なものさ。日本の悪しき慣習なのだろうけど、詳細な内容が契約事項に記載されることはないな。要は、ベンダー側からみるといわば“なんでもやります”という契約内容となっているんだ」
しかし、ユーザー企業のベンダー依存を促す関係性が、いつしかベンダーにロックインされ、ユーザー企業がさらに主体性を失う悪循環をもたらしているのだ。
「そうか。人材のことも契約のことも、アメリカでは考えられないな。ITは本来、ビジネスをする企業の幹(みき)となるものだ。ITは自社でイニシアティブをとり、自社で抱えるものだよ。つまり原則は、内製による開発ということになる。ただ、内製だからといって、プログラムをスクラッチ開発する、と言っているわけではないよ。むしろ、それは逆だ。とりわけ財務経理や人事関係、それと多くのビジネスに共通する受発注や在庫管理などの基幹業務は、パッケージソフトウェアを導入することが多い。なぜかというと、これらは現在、企業の競争力を産み出す差別化要素に直結しないからだ。せいぜい効率化する程度のこと。企業の競争力を向上するには、今までにない領域に進出したり、今までデータ化されていなかったものをデータ化して活用できるようにしたりして生み出される価値だ。顧客の購買意欲や流行、このようなものを分析対象のデータとしたいだろ。こういう領域にITを活用するべきだと現場に訴えるといいよ。そして、企業間の契約についても詳細なドキュメントが交わされる。数枚で終わっているということは考えられない。それでは何も決まっていない、に等しいんじゃないかな」
佐々木には文句のつけようがなく、苦笑いした。
「俺は、パッケージの型にはめようとするベンダーの担当者に、思わず『靴に足を合わせるのか?』と言ってしまった」
「ははは。よっぽど気が立っていたと見えるな。繰り返すが、パッケージは道具、手段だ。定型業務は道具で自動化すればいいが、新たな業務やシステムは創造していくしかない。経営者が、社員が、その組織で何を目指すのか、世の中にどんな価値を提供していくのか。そこが、すべての起点だよ」
遠藤は、カウンターに並ぶつまみに箸を伸ばした。
佐々木は、匠の口から聞く米国の状況に興味を持った。
「アメリカの契約がシビアであるとは聞いたことがある。けれども、内製が主流である、ということは知らなかった」
「だいたいSI契約という業態は、アメリカには存在しないしね」
「じゃあ、ベンダーはどんな業態になっているんだ」
「さっき言ったように一般の企業では、エンジニアを社内で抱え、業務視点でシステム開発を進める内製が主流だ。ちゃんとやっている会社は、開発したシステムは社内の情報システム資産台帳に登録され、変更管理が一元化されている。会社の中では、PMOが重要な役割を果たす。一方、受託開発で食っているベンダーというのは聞いたことがない。独自に開発した技術やサービスを売り込むベンチャーやスタートアップ。データを活用して新ビジネス、新市場を開拓するプラットフォーマー。チャレンジして失敗するやつも多いが、這い上がってくる奴も多い」
「開拓者精神か。・・・ところでPMOってなんだ」
「プロジェクト・マネジメント・オフィスの略で、企業の事業プログラムについて、その戦略を練り、舵取りをする組織だ。日本ではあまり存在しないようだね」
「ユーザー企業のPMOなんて初耳だよ。米国では、内製がユーザー企業では主流だというけど、システム開発の形態はどうなんだ。要件定義、設計、開発、データ移行、テスト、カットオーバーと言う流れなのか」
「基本は、アジャイル開発だ。アメリカではウォーターフォール方式で行われるプロジェクトは、今じゃほとんどないよ」
佐々木は目を丸くした。
「へー、アジャイル開発ねぇ。聞いたことがあるけど、俺自身経験がないから皆目見当がつかないな。日本の一般企業では、まだほとんどのプロジェクトがウォーターフォール方式だ」
「ウォーターフォール方式に、ベンダー丸投げのSI契約、ITに精通した人材が社内にいない。悪いけど、これではどんなプロジェクトも成功しそうにないな」
佐々木は、企業の業務におけるITの重要度、自社の根幹に関わる契約の位置付け、プロジェクトの体制など、日本と米国の本質的な差異を感じた。
店を出るとき、遠藤は、楽しかった。何かあれば、遠慮なく声をかけてくれ、と言った。1週間ほど、仕事で日本に滞在しているという。
親友を見送った佐々木は、高崎に帰るため東京駅から新幹線に乗り込んだ。遠藤から聞いた話は雲をつかむような話だったが、おかげで、現状を前より客観的に見ることができるような気がした。
(ただ、情報システム課という立場で、俺はどんな役回りを演じられるのだろうか)。
自分一人あがいて、どうこうなるものではない。部署を超えた協力が必要だ。何より、将来を見据えたB2CおよびB2Bにおける顧客管理のあり方、それに伴うこれまでのビジネスルールの見直し、いわば会社としてのビジネス戦略ありき。それあってのシステム開発である。上層部の結束と、業務部門の協力なしに進められるわけがない。
ただ、先日、総務部長の水沢が言った言葉には、一筋の光明が見えた気がした。呉服の桐生を取り巻く経営環境に厳しさが増し、経営陣が危機意識を抱いている。部署を超えた歩み寄りの気配があると。見方を変えれば、システム開発を立て直す上で、チャンスかもしれない、と佐々木は思った。
同時に、ユーザー企業のプロジェクトマネージャーとして、ぎくしゃくした日比谷ソフトウェアとの関係を修正する必要があった。
←第22話:一人娘の成長 第24話:発注者責任とイニシアティブ→