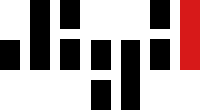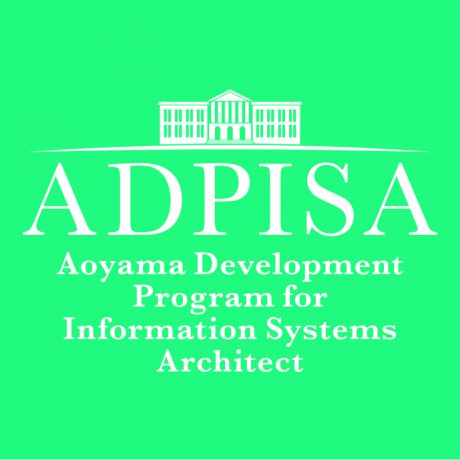宙に浮いた責任
2019年4月1日(月曜日) 午後3時、加藤と前田は約束の時間の10分前には、呉服の桐生に到着していた。ロビーに設置してあるショーウィンドウに飾られている着物は、爽やかな水色で仕立てられていた。前田はそれを見て、一昨年の夏、スキューバダイビングで潜った沖縄の海の青さを思い出した。
「うわー、綺麗な水色の着物ですね」
「これは、結城紬(ゆうきつむぎ)じゃないかな」
「加藤さん着物、詳しいんですか」
「いや、そんなことないけど。本場の結城紬は、最高級の絹織物だよ。起源は奈良時代で、常陸国、今の栃木県や茨城県のあたりで作り出された。国の重要無形文化財にも選ばれていたはずだよ」
「へー、意外。私は全然着物のこと知らなくて。加藤さん、ちょっと見直しちゃいました」
「ははは、随分見くびられたもんだな」
ちょうど5分前に受付の前に立つと、「いらっしゃいませ」と声がかけられた。
「日比谷ソフトウェアの加藤です。情報システム課の佐々木課長とのお約束があり伺いました」
受付の女性が立ち上がり、「お待ちしておりました。会議室にご案内いたします」といい、ロビーに隣接した3つある会議室のひとつに二人を案内した。
会議室に入ると、二人は緊張した面持ちで立ったまま佐々木を待った。
しばらくすると、佐々木が会議室のドアを開けた。加藤に顔を向けて「いや、どうもどうも。プロジェクトの準備はどう?」と声をかけた。
加藤は「順調です。今日は来週のキックオフについての打ち合わせでお伺いしました」と対応した。
続けて「今回のプロジェクトマネージャーを紹介します。私の部下の前田です」
前田は「前田と申します。今回は御社のプロジェクトを担当させていただくことになりました。よろしくお願いします」と言い、軽く会釈しながら名刺入れから名刺を1枚出して佐々木に手渡した。
「ごめん、名刺持ってきてないなー」と言いながら佐々木は前田から名刺を受け取り、加藤に向かって「加藤さんが責任者じゃないの?」と尋ねた。
「今回、前田がプロジェクトマネージャーで取り仕切ります。私は彼女をサポートする立場です」
「パッケージだからね、女性でも大丈夫か」と佐々木は一人で納得し、「今回のシステム開発はおたくに任せるから、私は大船に乗ったつもりでいるよ。パッケージを採用したのもそのためだから。後はよろしく頼みます」とペコリと頭を下げた。
「承知しました」と加藤は答えた。
3人が席に着くと、前田は佐々木の前の机の上に資料を丁寧に置いた。
前田は「それでは、キックオフの資料を説明させていただきます」といい、プロジェクトの目的や内容など、資料を読み上げながら説明した。
佐々木は何度もうなずきながら前田の説明を聞いていたが、プロジェクト体制について説明した直後に、突然、佐々木が口を開いた。
ステアリングコミッティが最上段にあり、その下にプロジェクトチームが描かれていた。ステアリングコミッティはプロジェクトに関する意思決定機関である。桐生藤四郎を筆頭に、販売部長の高橋、直販部長の新井、総務部長の水沢など関係部署の部長クラス、日比谷ソフトウェアは山本常務が名を連ねていた。
プロジェクトチームは、開発プロジェクトを実際に遂行するメンバーで構成される。発注者である呉服の桐生からは、情報システム課長の佐々木が、日比谷ソフトウェアからは前田が、それぞれ責任者(プロジェクトマネージャー)に任命されていた。
「何かおかしくない?」と佐々木が言った。
前田は、資料のどこかに誤字があるかと思い、出力したプリントの上に視線を走らせた。
佐々木は体制図を指差した。
「私が一番上にいるんだけど。このプロジェクトはおたくが請け負ってくれるんだよね。責任のある人が一番上にいないとおかしいんじゃない。前田さんがこのプロジェクトの責任者だよね」と念を押すような口調で話した。
「確かにうちの会社、つまり呉服の桐生として、責任があるのかもしれないけど、私は今回使うパッケージのことは全然わからないし、失敗したときに責任とってくれ、と言われても無理だよ・・・」と佐々木はまるで他人事のように話した。
会議室に沈黙が流れた。
前田は、佐々木が何を言っているのかよくわからなかった。プロジェクトが始まってもいない段階なのに、あたかも失敗を前提としたような言い方であり、なおかつ、失敗の責任を押し付けられたくない、という風に聞こえた。
加藤にも、佐々木がいう不満の原因はよくわからなかったが、その言動からは、このプロジェクトにあまり深く立ち入りたくない、渋々やらされている、というネガティブな心証を受けた。
前田は、プロジェクトマネージャーは自分だ、と己を奮い立たせ、佐々木の顔をしっかりと見て言った。
「本プロジェクトでは、ユーザー企業の責任者の方が、プロジェクトオーナーとして、プロジェクトのトップに立っていただきます」
「本当にそうなの? せいぜい同格ぐらいで勘弁してくださいよ。この前あった別のプロジェクトでは、あるベンダーのプロジェクトマネージャーと私が同格に、ということで仕方なく引き受けたんだけど。加藤さん、そのあたりどうなの?」と、佐々木は前田の説明に納得せず、加藤に向かって尋ねた。
「以前はそのような両社のプロジェクトマネージャーを同格とする体制図だったこともありました。しかし・・・」と加藤が言った途端、佐々木は言葉を遮るように、
「じゃあ、今回もそうしなさいよ!」と命令口調で加藤に言った。
その勢いに押されたかしぶしぶ加藤は、
「わかりました。そのようにします」と答えた。
加藤は、体制図の佐々木修の隣に、ペンで丸を描いた。そして、一段下に書かれていた「前田理沙」の文字とその丸の間を、線で結んだ。
その途端、前田は、(えっ!どういうこと?)と戸惑いながら加藤の顔を見た。
加藤は(ここで佐々木と話をこじらせて、明後日のキックオフミーティングに差し障り出るとまずい)と考えた。前田には、佐々木に気づかれないように首を小さく左右に振りながら説明の続きを促した。今は堪えて、後で改めて話そう、という意図だった。
前田は納得しないまま、説明を続けた。体制図以外は佐々木からの指摘はなく、うなずきながら前田の説明を聞いていた。
しかし前田は、体制図のことばかり考えていた。ひとしきり前田の説明が終わると、佐々木は、
「明後日のキックオフは、社長や販売部長など首脳陣が出席するから、よろしく頼むね」と念押しした。
加藤は「かしこまりました」と答えた。
キックオフミーティングの資料説明を終え、多少雑談したものの、30分ほどで打ち合わせは終了した。
二人が呉服の桐生のロビーを出た途端、前田は「呉服の桐生のプロジェクトマネージャーである佐々木さんと私が同格である体制図はおかしいと思います。だって、『プロジェクトマネージャーはユーザー企業から選ぶべき、責任者は一人であるべき』って研修で学びました!」
呉服の桐生の本社前にいるため、誰に話を聞かれるかわからない。加藤は前田を促し、高崎駅に向かって足早に歩き始めた。
「確かに基本はそうだけど、ケース・バイ・ケースだから・・・。それに佐々木さんとのトラブルは避けたいし・・・。でも、前田のいうこともわかる。プロジェクトを成功させるために一緒に進もう、という意欲が感じられなかった」
「はい。そちらが勝手にプロジェクトを進めてよ、みたいな突き放した言い方に聞こえました。佐々木さんって、日比谷ソフトウェアへ丸投げするつもりですよね」
「まあ、初対面の相手と最初からうまくいくことは、滅多にないよ。気を悪くするな。相手の言い分も聞きながら、少しずつ歩み寄っていこう」と加藤は前田をなだめた。
前田は納得せずまだ言いたいことがあったが、社会人を10年近く続けていると、こういうこともある、ということを少しばかりは学んでおり、それ以上は言わなかった。
←第6話:日比谷ソフトウェアの女性プロマネ 第8話:キックオフミーティング→