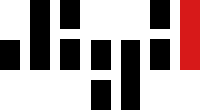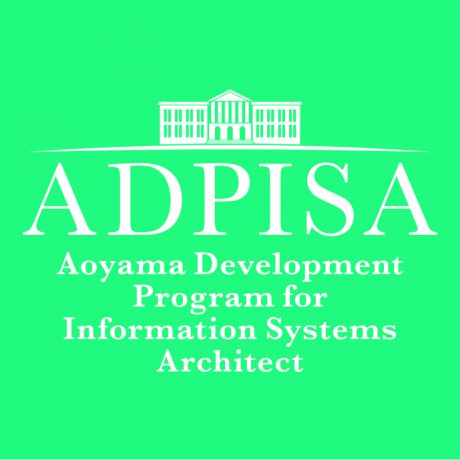第1章 すれ違いの契約
着物の復権にかける呉服屋4代目
着物(きもの)が日本人の暮らしの中から遠のいて久しい。
衣食住のスタイルが急速に欧米化したのは1970年代。その頃を境にして、私たちの暮らしぶりも大きく様変わりした。
今日でも、七五三、大学の入学式・卒業式、結婚式など、人生の節目にあたる行事の折に着物姿の人々を目にすることはある。「晴れ着」はハレの日に着るから文字通りそう呼ばれる。また、華道、茶道、日本舞踊、お琴などの邦楽といったお稽古事をたしなむ人や、仕事柄、着物を必要とする商売に関わる人の着物姿は少なくない。ただ、一般の人が日常の着衣として身につけることは滅多になくなった。戦後、洋服が急速に普及するまでは、市井の人の手に届く木綿や麻の着物は生活必需品だった。現在では、人生で幾度も袖を通すわけではないし、着る方法もよくわからない、ということで、着付けとセットになったレンタル品の利用が増えている。
業界の統計調査によると、着物の売上金額は昭和末期のピーク時には1.8兆円ほどあった。それが令和に入ったいまでは、約2,800億円の市場規模にとどまる。平成という時代を通り過ぎる間に、7分の1あまりに縮小した。ちなみに、日本の衣料品全体の市場規模で見ると、近年は14兆円程度で推移しているとのデータもある。
2019年5月中旬、群馬県高崎市に本社を置く「呉服の桐生」では4代目社長である桐生藤四郎が、3月締めの本決算報告に向けた打ち合わせと、高崎市内にある直営店の視察を終えたところだった。
43歳の藤四郎は社長に就任した5年ほど前から、年間の大半を着物で過ごすようになった。着物には大きく、袷(あわせ)、単衣(ひとえ)、夏着物の3種類がある。袷は着物に胴裏と八掛という裏地をつけて仕立て、晩秋から春先にかけて身につける。夏と秋は裏地のない夏着物や単衣で涼しく過ごす。秋から冬、冬から春への季節の変わり目の時期は、胴裏をつけない袷を着て寒暖を調整する。冬本番の寒さでは着物の上からさらにコートを羽織るとうまくしのげる。ただ近年は温暖化する気候のため、かつて10月から5月頃まで着るのが当たり前だった袷を着る期間が、12月から3月にかけてと、短くなってきた。
さて呉服の桐生にとって、卒業、入学、入社、転勤の時期が一段落する5月は客足が鈍る。
ただ今年は例年と比べて年明けから全体的に好調だった。5月に平成から令和への改元が行われ、一連の皇室行事が前年から、ニュースなどでつぶさに報じられた。令和の天皇陛下は126代目。日本に続く皇室の歴史を改めて感じさせる年は、着物の販売にもプラスに作用したようだ。
やがて夏が来る。夏祭りや花火大会が盛んに行われる7月、8月は呉服の桐生の売上の3割を占める浴衣、夏着物の書き入れ時期である。手ぬぐい、扇子など浴衣に合わせた和装小物も売れ行きが伸びる。今年は令和元年、最初の夏である。キャンペーンを打ち出さなければならない。
「そして来年は、2020年東京オリンピック・パラリンピックだ。海外の人にも着物文化を経験してもらい、世界に着物文化を発信する絶好の機会が来る」
そう藤四郎は考えていた。
呉服の桐生における2018年度連結売上高は80億円強だ。業績はこの10年ほど、緩やかに下降線をたどるが、縮小しつつある業界の中では、大手と言われる部類に入る。売上の6割以上を占めるのは、卸問屋経由で主にデパート・百貨店で販売される着物など。3割強が主に、東京と横浜市、高崎市、の直営店舗での販売や、仕立て直しなど顧客の利用する着物の手入れに関わる売上である。
呉服の桐生は、大正10年(1921年)に群馬県高崎市で創業した。創業者は、桐生善一郎である。
桐生家のルーツはもともと絹を生産する地元の養蚕農家に遡る。明治期になると製糸業にも力を入れた。生糸は乾燥させた繭から生産する。殖産興業政策が掲げられ、生糸の海外輸出が盛んになった当時、群馬から横浜へ生糸を輸送するための鉄道が他の地域に先駆けて整備されている。1889年には甲武鉄道(現在のJR中央線)が、1908年には横浜鉄道(同JR横浜線)が、長野、山梨、群馬、埼玉の西部地域などから生糸を横浜港に向けて運ぶため、相次いで開通した。その頃、生糸で儲けた桐生家は、絹を反物にする工場を地元の高崎に設立した。創業者の善一郎は、絹織物の販売も始めた。その子、良二郎が家業を継いで販路を首都圏に広げた。高度経済成長期を迎えると着物の需要がピークを迎える。良二郎の子である又三郎が3代目となり、最盛期は年商600億円規模に達した。桐生藤四郎はその老舗呉服店の四代目を任されている。
従業員数は現在、契約社員を含めて480名。卸問屋や、デパートや百貨店を担当する販売部員が、その半数を占めている。
藤四郎は社会人になって、すぐ呉服の桐生に入社したわけではない。映画好きだった藤四郎は、学生時代は映画部に所属し、自ら脚本を書いて仲間と自主映画製作に没頭していたこともあった。大学卒業後は、家業を継ぐかどうか迷ったが、周囲の反対を受けながらも、映像制作会社に勤めた。いずれは父の後を継ぐのだ、と周りから言われてきた藤四郎が映画の世界に飛び込んだ理由には、着物業界ではない外の世界を見てみたい、という思いがあった。父親や自分に干渉する周囲への、若者らしい反抗心もあった。しかし、映像制作の世界に関わるようになってから、映像で表現される日本の文化や着物についてさらなる可能性を感じるようになった。どのように作られ、人の手に渡るのか。調べるうちに、海外から評価される日本の衣・食・住の文化の魅力に引き込まれていた。
6年間、世話になった映像制作会社には、家業を継ぐことを伝え、退職の希望を受け入れてもらった。それから藤四郎は、呉服の桐生で働き始めた。28歳の時だった。
10年の年月が過ぎた2014年。63歳の又三郎が脳梗塞で倒れた。辛うじて生還したものの体には麻痺が残った。又三郎が38歳の藤四郎に事業を任せたいと打ち明けたのはその頃である。藤四郎としては、もう少し色々な現場を回り、知識や経験を身につけたいというのが本音だった。しかし、リハビリに励むも、思うように体が利かなくなった父親を見て、考えが変わり始めた。専務で販売部長を兼務する高橋忠孝も手助けしてくれるという。高橋は、又三郎が駆け出しの頃から苦楽を共にしてきた会社の番頭役である。年齢は又三郎より2つ下で、この時、61歳だった。藤四郎は覚悟を決めた。あれから約5年。藤四郎は今年43歳を迎えた。
藤四郎は四代目を継ぐ前、販売部に在籍していた頃から、「呉服の桐生」ブランドを海外に打ち出す直販の取り組みを意識的に強化してきた。
外国人が日本文化に寄せる関心は近年急速に高まっている。社長に就任して間もない 2015年7月、藤四郎はイタリアのミラノ万博における KIMONO for Italy のパレードに、着物を着て参加した。陽気なイタリアーノたちは着物を珍しがり、スマートフォンで互いに写真を撮りあい、SNSに投稿しあった。こうした海外からの高い関心をいかに自社ビジネスにつなげていくか、着物文化の発展につなげていくかが、次の10年を生き延びるための鍵だ、と藤四郎は感じた。
藤四郎が目指す着物の理想は、着物は特別な時に着用する衣装から、日常着られる衣類へと転換することだ。洋服を頭から否定する気はない。それぞれに良いところがある。例えば、忙しい人にとって、衣類の手入れは今日の洋服の方が便利だ。しかし、週末など少し時間がある時には選択肢として加えてほしい。着る人の個性はそれぞれに異なる。着る人の個性に寄り添う着物を仕立て、着ることの楽しみ、豊かさを肌で知って欲しい。
そのために、呉服の桐生では、直営店舗を通じた直販の比率を高めることが重要だ、と考えていた。手軽な和装小物などは、今後はECサイトを通じた問い合わせや取引にするなど工夫しても良いだろう。なるべく流通をシンプルにし、その分、価格も抑えて、より多くの人の手に着物が届くようにすることで日本の文化を育みたい、という理想があった。
これからは、販売部、直販部の力を合わせて、新しい市場開拓に挑まなければならない。着物を着て日本文化を体験してもらうとともに、日本文化の発信者としての顧客を育てていくためである。
そして、約1年後の来年2020年4月には、この事業展開を支援する顧客管理システムが完成し、稼働する計画だった。