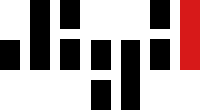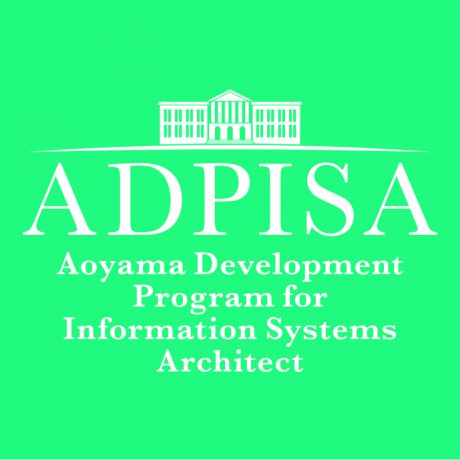第9章 明けない夜はない
第9章 明けない夜はない
創業100年目の門出
日比谷ソフトウェアと2020年4月に交わした再契約の後から着手した、2020年11月を見込んでいた優先順位の高いシステム開発の第一フェーズが完了した。優先順位づけをした開発がうまくいった。すなわち、佐々木が遠藤と同窓会の後に話した、システム化が必要な真に重要な業務は実は業務全体の2割ほどしかない、という話だ。思い切って、呉服の桐生にとって重要な直販系のモデルを中心に、CRMで扱うデータや機能を絞った。その結果、この部分は現場の反応は思ったより良かった。そうした声から高品質なプロダクトになったことを佐々木は、感じていた。前回の調査成果に基づく資産が生かされたこともあったが、日比谷ソフトウェアの設計・開発チームが優先順位に基づいて動くシステムをリリースし、それを元に改良を重ねていくやり方が奏功した。社内では顧客を中心とするチャネル連携を機に、旧来のマーケティング事業を発展・強化する新事業部の準備組織が立ち上げられた。直販部と企画部がリードする事業だった。
バックログに残った残りの要求部分は、粛々とやるだけだ。
「システムに完成形はありません。永遠にβ版をよくしていくようなものなのです。システムは建物ではなく、生物のように常に新陳代謝しています」と、スクラムマスターの山田が口癖のように言っていた。佐々木は、ふと子供の頃に遊んだ独楽(コマ)を思い返した。
(コマは回っている時が安定している状態だ。止まってしまったらコマの働きをしているとはいえない。情報システムもコマに似ているかもしれない)
2020年12月7日(月)、佐々木は藤四郎から呼び出しを受けた。
「総務部情報システム課は、来年1月から情報システム部に格上げします。正式な辞令は間もなく出ますが、佐々木さんの肩書きは、情報システム部長になります。これからは、桐生全体のシステムを見てください」。
佐々木は、「承知しました」と深々と頭を下げた。身が引き締まるような思いがした。
遠藤匠にはメールで近況を伝えた。お前からのアドバイスがなかったら無理だった、と礼を書いて送ると遠藤からは、プロジェクトの成功と新しい役職に就くことを祝う返信が届いた。彼もまた日米の企業間で組む医療関係の事業を支援しているとのことだった。
自宅に戻り、妻に伝えると「無理しないでね」と笑った。娘の希望にはLINEで伝えた。希望は相変わらず忙しいらしく、年末年始に戻ってきた時にお祝いをしてあげる、と返事をくれた。
ただ、佐々木は手放しでも喜んでいられなかった。すでに、CRMシステム第二フェーズとして販売部を含む他の部門とのデータ連携の拡充に向けたスプリントを試行錯誤しながら進めていた。
一連のスプリントでは、直営店で着物を購入してくれたことのある複数名の顧客の同意を得てモニターになってもらい、着物に対してどのようなニーズを持っているか、ヒアリングをし、その結果をビジネス要求やシステム要件に反映することにした。20代から30代、40代前半にかけては、価格が高い、着付けの仕方がわからない、またどのようにコーディネートすればいいか知りたい、祖父母や両親から受け継いだ着物をどう活用していけば良いか悩んでいる、といった声が多かった。三上や前田はそうした声から、CRMシステムで集約し、組織的に活用するデータを検討していった。
さらに情報システム部となれば、社内の若手人材の育成にも目を配る必要があった。社長の藤四郎に相談し、次のように要望を伝えていた。遠藤からのアドバイスを思い出しながらだ。それは、各業務部門の担当者の中から見所のある人材を情報システム部の研修に参加してもらい、IT知識の全社的な底上げとともに、各業務部門が調達・開発・運用する一定規模以上のシステムを、クラウド環境導入を機に一元的に資産管理できるようにしたいということだ。情報システム部も社内の業務知識とITスキルの蓄積を図る意図があった。藤四郎は「その提案を前向きに検討する」と言った。
社内にも、藤四郎社長の鶴の一声が予想以上に響いているように佐々木には見えた。
販売部長の高橋が、プロジェクトに協力し始めてから、古田を含むベテラン社員も以前より積極的に力を貸してくれるようになっていた。販売部が、百貨店やデパートに呉服の桐生が進めている新システムのことを話すと、意外にも乗り気だったことが大きかった。百貨店やデパートも、新しい顧客獲得に向けて、頭を悩ませていた。状況を打開するためにも、新たなデータマーケティングを一緒に展開していきたい、相互にチャネルから入る情報を共有して新たなビジネス価値を生み出そう、という機運が高まっていた。無論、まだどのような方向性になるか未知数の部分もあった。だが、組織内だけでなく、組織を越えた顧客中心のデータ活用へと動いていることを、販売部の社員を含めて多くが感じていた。
日比谷ソフトウェアでは、シニア・プロジェクトマネージャーの加藤が新たなプロジェクトの統括を担う話が浮上していた。加藤が、そろそろ呉服の桐生プロジェクトの方は、前田に任せても良いかな、と考え始めていた時だった。
前田はその頃、アジャイル開発の第二フェーズの推進にやりがいを感じていた。高崎と日比谷を行ったり来たりしつつ、リモートで開発に参加しながら慌ただしい日々を送っていた。そんな中、前田のメッセンジャーに三上からの着信があった。よかったら近々一緒に晩ご飯でもいかがですか、という誘いだった。「まだ前田さんとちゃんと話したことがなかったので。ご都合を聞かせてください」と記されていた。
三上からの提案に、前田は驚きつつも少し舞い上がっている自分への戸惑いを隠せなかった。
慌ただしい2020年も残りわずかを数えるほどになっていた。
(了)