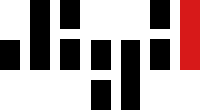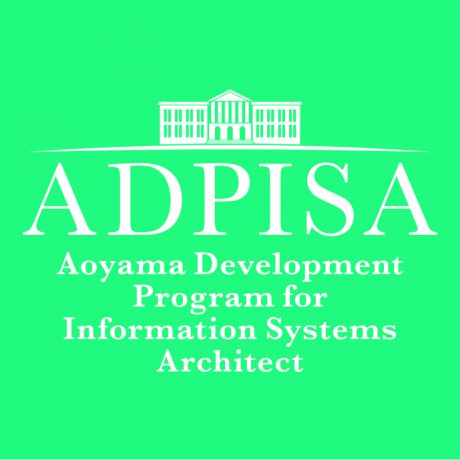前例なきチャレンジ
まず思い浮かぶのは、プロジェクトマネジメントだ。
「プロジェクトマネージャーを誰が担当するか」ということで、日比谷ソフトウェアの加藤、前田と揉めた。佐々木は、朝日製作所と組むはずのコンペが不発だったことを引きずって、頭が切り替えられずにいた。
そのあと、日比谷ソフトウェアの前田がCRMシステムに入力するデータの取得方法について販売部の古田に説明したところ、取引先に迷惑をかけるのか、と神経を逆撫でし、販売部との信頼関係にヒビが入った。
佐々木が携わった過去のプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはベンダーに任せることが普通だった。佐々木は、ベンダーの報告を聞きながら基本的に進捗を管理し、たまに何か社内の現場からクレームがあるとき、間に立つ仲裁役でよかった。今回のような状況にまで、事態がこじれた記憶はない。
これまでのプロジェクトと今回のプロジェクトでは何が違うのか、佐々木は考えた。これまでのプロジェクトは既存の業務を効率化する、電算化する、現行システムにちょっとした機能を加えるものだった。ベースには既存の業務やシステムがあり、プロジェクト後の姿がある程度、見通せた。ところが今回のこのプロジェクトは、新規ビジネスを支援するシステムを作り上げるものだ。これまでと違い、不確実さへの挑戦というべきものだった。不確実なものを確実にしていくには会社が一つになる必要があったのではないか。
販売部は日比谷ソフトウェアとの距離感だけでなく、呉服の桐生の直販部や企画部とも終始溝があった。総務部や情報システム課は販売部から「会社のプロフィットセンターではないから」と一段下に見られていた。部署間における見えない力の優劣が、今回のプロジェクトがまとまらない遠因にあった。他部門から選定されたメンバーたちも、販売部に遠慮してか、当事者意識を欠いていた。販売部に任せました、というどこか他人事のような雰囲気が漂っていた。そのために、仕様が詳細になるほど、生じる齟齬が大きくなったのだ、と佐々木は思った。
何をどこまでやるか、各部門間での調整は進まなかった。プロジェクトのスコープも曖昧になった。何か聞かれたら答える、という指示待ちや受け身の姿勢は、縦割り組織が陥りやすい弱みだ。総務部長経由で、業務部から取りまとめを依頼された業務管理課の三上も現場との間で板挟みになって、苦労していた。
関係者間での進捗に関する情報共有やコミュニケーションの場は頻繁にあった。会議体は、毎週の火曜日の定例ミーティングに加え、2019年11月からは、必要に応じて金曜日にも追加された。週次のミーティングでは、要求について言った・言わない、機能を盛り込む・盛り込まない、という内容に終始し、混乱していた。
しかし、月に1度、呉服の桐生で開催されるプロジェクト進捗会議においては、上層部に余計な心配をかけないよう、開発現場の混乱を伝えず、曖昧な言い回しで状況を報告していた。その結果、社長や専務も当初、危機感はなかったのだろう。業務部門担当者におけるユーザー受け入れテスト時のクレームを聞いて、突如、問題が発覚したような印象を受けたに違いない。
佐々木自身も、「プロジェクトマネージャー」として動けなかった。佐々木は全社的に新たな業務を作り出すシステム開発案件として、帯紐や扇子など和装小物を扱うECサイトの立ち上げなどに携わってきた。それは例外的で、主な仕事は財務経理や人事総務など、既存業務全般を支える情報システムの再構築、またはハードウェアの更新、リホスト、リビルド、COBOLのコード資産をJavaなどの言語に書き換えるリライト、いわゆるモダナイゼーションというものである。他には、ネットワークの増強やセキュリティ強化などITインフラの整備を主に手がけてきた。
呉服の桐生における顧客の定義を見直し、業務のやり方を変える、という意味では本来、プロジェクトのスコープは、異なる部署間をまたがるものだ。業務部門のデータモデルやプロセスモデルを変えるには、現場との間に十分な信頼の醸成が必要である。それもないまま躊躇しているうちに、現場からの要求に歯止めが効かなくなった。販売部における現状の業務システムで実現している機能が、新たに導入するCRMに盛り込まれず、やり方が変わることに現場が強く反発した。だがプロジェクトを進めるために、ある時点で、機能を確定した、要件定義工程を終えた、というサイン(署名)は、たとえ形式的であってもしている。その意味では、呉服の桐生側にも非はあった。
しかし、要求が満たされていないことが発覚したのがユーザー受け入れテストの段階だったのは遅すぎた。業務部門としてあって当たり前の機能面の要求が、漏れていたケースが多数指摘された。それはAs-Isを把握するため、現場にヒアリング調査を行った日比谷ソフトウェア側の落ち度もあるだろう。その結果、大量の手戻りが発生し、変更がコントロール不能になってしまった。現行の機能にプラスして、パッケージソフトウェアの新機能を利用する、となって機能爆発してしまった。
要求のシステムへの反映は日比谷ソフトウェアに任せるしかなかった。呉服の桐生の情報システム課に、要求を反映するだけの技術力はない。佐々木は調整役としての枠から、外に足を踏み出せなかった。同じ組織に長年どっぷり浸かっているうちに、いつしか受け身なマインドが佐々木自身に染み付いていたのかもしれなかった。
佐々木がうなだれていると、部屋の扉の向こうから、「あなた。もう少しで晩御飯の用意ができるわよー」という妻、雪枝の声が聞こえた。
「ああ。わかった。一段落したら、そっちに行く」
「はーい」という、のんびりした返事が聞こえた。
佐々木は部屋のガラス窓から空を見た。気づけば、辺りは薄暮に包まれ、街灯の明かりが見え始めていた。佐々木は、両腕を上に伸ばして、深呼吸をした。