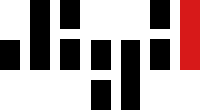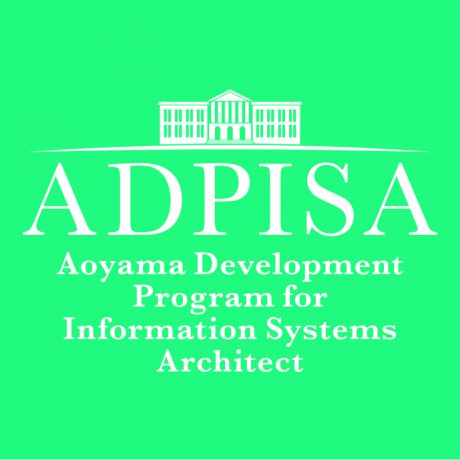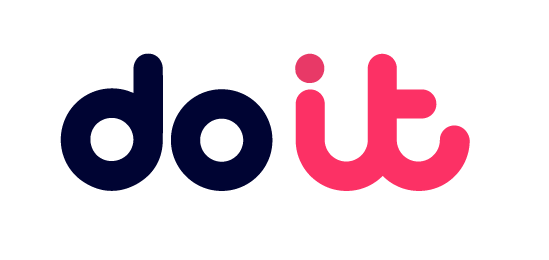掛け違えたボタン
加藤は、佐々木との打ち合わせを終え、呉服の桐生本社を後にした。
加藤は、シニア・プロマネという肩書をもらってはいるものの正直、人間関係の調整は得意な方ではない。前田の歯に衣着せぬ物言いをうらやましく思うことさえある。しかしながら、今回の件で前田には一言釘を刺しておかなければならない、と思った。
「前田さんが、CRMに関して販売部の古田さんや佐々木さんに説明したことは正しいと俺も思うよ。だけど連中は、『昭和の男』なんだ。正論で押せば角が立つくらい察しがつくだろう。その辺は配慮してくれよ」
加藤は、いつもとは違って強い口調で前田に注意を促した。佐々木からの要求を断ったことで、前田に貸しを作った気がしていたのだ。
(ついでに言うなら、僕も「昭和の男」なんだから、少しは気をつかってくれ)とまでは、口には出さないのが加藤流である。
「でも加藤さん、今回のプロジェクトではカスタマイズ部分を最小限にしないと、納期を守れそうにありません。特に販売部は、『仕事のやり方はこれまでと変えなくていい』なんて言ってますけど、既存のやり方にこだわればカスタマイズの工数が増えます。コストもオーバーすることになります。そのことは、あちらにも理解してもらわないと。赤字になることが分かっているプロジェクトなら、やる意味がありません」
前田の言い分は、まったくその通りだった。
前田は、CRMパッケージであるSF1を導入するためのTo beをまとめながら、呉服の桐生にとっては、カスタマー(顧客)が二種類あることに気付いていた。現在の桐生の売上の3分の2以上を支えているのが専務の高橋忠孝率いる販売部であり、販売部員は「呉服の桐生」社員の半数を占めている。
前田は、SF1をBtoCベースで使うつもりだった。だが、販売部の業務は、相手が卸店なのだからBtoBの業務である。SF1が得意とするダイレクトメールの発送やアンケート調査などのデータ分析機能は生きてこない。どちらかと言えば営業担当者への行動管理をするような側面もあるので、その導入は一筋縄では行かないことが懸念された。
販売部員にとっての「顧客」とは、自分の担当する、着物の販売店・百貨店のことであった。一方、社長の桐生藤四郎が担当している直販部隊にとって、3店舗ある桐生の直販店舗に訪れるお客様こそが「顧客」である。この二つの「顧客」を同じもの、として扱うことはできない。
前田は、プロジェクトの会議に販売部と直販部がなぜ同席しないのかが次第にわかってきた気がした。
おそらく社長の藤四郎は、このプロジェクトを自ら思い入れのある直販部のためのプロジェクトとして始めたのだ。そのことを販売部長で専務の高橋にきちんと伝えなかったために、実際の稼ぎ頭である販売部にも同じCRMが使えるものとボタンを掛け違えたまま、プロジェクトが走り出してしまったのだ。
販売部員は、長年に渡って顧客である販売店との関係を築いてきたベテランが多く、売り上げに応じたインセンティブ(歩合給)の比率が高いため、部員相互が情報共有をして顧客に対峙するという意識が乏しい。呉服店が開催する展示会に赴いて地道に手伝いをし、場合によっては、身銭を切って店主を接待するなど業務マニュアルには存在しない気配りをすることで、その信頼関係を維持してきた。それぞれの商談相手が呉服の桐生に何を望んでいるのかは、同僚にさえ秘匿すべき大切なメシの種というわけである。
このような長年に渡る人間関係を重視する販売部員に対して、桐生の直営店を運営する直販部は、商品を購入するお客様の情報を直接管理したいという意欲に溢れていた。特に二十歳前の女性の名簿情報は貴重であり、それまでお付き合いのなかった方が、成人式のタイミングで桐生の新たなお客様となる可能性は、他のどんなイベントよりも高いからだ。18、19才の娘さんに適切なタイミングでもってダイレクトメールを出すことができて、直営店が開催するイベントに参加してもらうことさえできれば、成約の可能性は限りなく高まってくる。一度何らかの形で関係を作り情報が得られれば、本人の友達や姉妹関係など顧客が広がる可能性も高まってくる。CRMが生きる業態なのである。