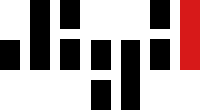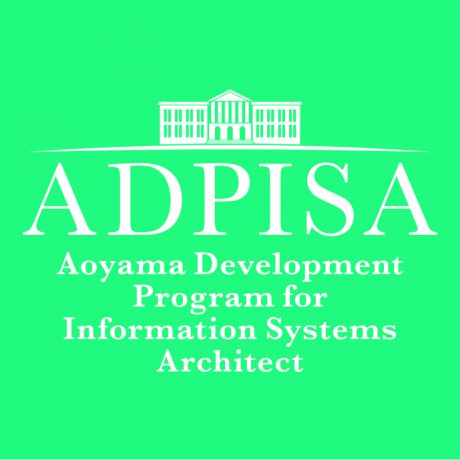第6章 それぞれの変化
うなだれる大番頭
2月13日(木曜日)、呉服の桐生に緊張が走った。デパートや百貨店などへの着物の販売を主に手がけていた卸問屋の中川屋が、倒産した、という一報が飛び込んできたのである。呉服の桐生が懇意にしていた老舗の事業者だった。取引先のデパートや百貨店の売場縮小と店舗の閉鎖による販売不振が続いていたことが、経営破綻につながった、という。
高橋は倒産の知らせを、販売部の部下から聞いた。中川屋は、高橋が若い頃から付き合いのある問屋だった。中川屋の社長はかつて業界の風雲児と呼ばれる剛腕で、全国に事業展開したことで一時期、脚光を浴びたことがあった。高橋も、公私共々並々ならぬ世話を受けた恩がある人物だった。
中小の卸問屋は、年々苦境に立たされている。そのことは高橋も日々接する顧客、すなわち取引先の仕事ぶりから察していた。ただ、まさか、あの大手の中川屋が、という信じられない思いがあった。同時に、そう遠くない時期にこの日が来たに違いないと思う、もうひとりの自分がいた。
着物の市場も、時代も、また大きな転換点を迎えて変わり始めている。卸店などの先にある百貨店や催事を通じて、限られたひいきの常連客に繰り返し着物を買ってもらう、という昔ながらのやり方が通用しなくなってきた。着物に対する潜在需要がないのではない。しかし、小売、流通、そしてメーカーが殻を破り、自ら需要を掘り起こす努力を重ねなければ、そして人々に喜ばれる価値を提供し続けられなければ、着物に関わる産業そのものが潰れてしまうだろう。呉服の桐生は生き延びることができるだろうか。安泰であるとの保証はどこにもない。高橋は目の前の現実を受け入れざるを得なかった。
日比谷ソフトウェアからの再提案書が、総務部長の水沢経由で上層部に上がってきたのは、その知らせの直後であった。
2月14日(金曜日)。緊急開催されたステアリングコミッティで報告がされると、高橋はうーむ、と唸って目を閉じた。藤四郎は、壁を凝視しながら黙考していた。
しばらくして藤四郎はメンバーに告げた。
「当社としては、CRMの導入方針を曲げるものではありません。販売部だけに依存しない直販事業の強化、これが10年先に生き残る会社の事業方針として重要であるという認識は変わりません。みなさん、中川屋の倒産は、ご存知の通りです。これは対岸の火事ではありません。当社におけるシステム化の意味合いもこれまでとは違います。既存システムの焼き直し、ではなくリスクをとった上での新しい挑戦なのです。今回のプロジェクトは、日比谷ソフトウェアに非があるかもしれない。しかし当社にも課題があるでしょう。過去の延長線上でシステム化をすると考えていなかったか。価値を提供するべき顧客とは誰か。システム化の意味について、ボタンを掛け違えたまま進めていなかったか。もう一度、原点に立ち返り、我々自身の手で組織と業務を変革する。リスクを恐れずに前進しましょう」
沈黙していた販売部の高橋が口を開いた。
「わかりました。社長。販売部も全面的に協力致します」。
その口ぶりはいつになく神妙だった。中川屋の経営破綻は高橋には相当堪えているようだった。
日比谷ソフトウェア側との再契約交渉を改めて進める。呉服の桐生側の幹部層の意見はほぼ固まった。
2月22日(土曜日)、佐々木は家の自室で考えごとをしていた。
先週2月17日(月曜日)、佐々木は、総務部長の水沢からプロジェクトの立て直しの命を受けた。
「佐々木君、上から改めてゴーサインが出た。うちの会社を左右する大事なプロジェクト、という認識で経営上層部がようやく一致してきた。意見にもまとまりが出てきている。今度こそ、待ったなし、だ。現場のことは頼むよ」
「はい」
「それで、だ。日比谷ソフトウェアと再契約にあたって、プロジェクトの進め方の提案を、呉服の桐生のプロジェクトマネージャーとして君にまとめてほしい。なんとか来月、3月の第一週までにまとめられるか」
「わかりました」と、返事をしたものの、佐々木には都合の良い銀の弾丸も魔法の杖もなかった。
先週の水沢の話を思い出しながら、佐々木は高崎にある自宅で、前回のシステム開発がなぜ躓いたのか、問題点をもういちど整理していた。
←第19話:暗礁に乗り上げたプロジェクト 第21話:前例なきチャレンジ→